- 医学部受験マニュアルTOP
- 東京都の医学部一覧
- 東邦大学医学部

| 口コミ |
|
|---|---|
| 偏差値 | 66.5(偏差値 34位/82校) ※医学部医学科がある全82大学での順位 |
|
学生数 ※医学部医学科の数値 |
715人【男性:48.1%・女性:51.9%】 (女子比率 3位/41校) |
| 6年間で 必要な学費 |
25,800,000円
(学費 8位/31校) ※私立の医学部医学科がある31大学での順位 |
| 医師国家試験 合格率 |
94%(合格率 35位/82校) |
東邦大学医学部の偏差値
[PR]東邦大学医学部におすすめの医学部専門予備校・塾・家庭教師
東邦大学医学部の学費
| 6年間学費総額 |
25,800,000円
ランキング 8位/31校
※私立の医学部医学科がある31大学での順位 |
||
|---|---|---|---|
| 1年次学費総額 | 5,297,800円 | 2年次以降学費(年間) | 4,200,000円 |
| 1年次学費 | 入学金 | 1,500,000円 |
|---|---|---|
| 授業料 | 2,500,000円 | |
| 教育充実費 | 500,000円 | |
| 委託徴収金 | 497,800円 | |
| その他 | 300,000円 | |
| 合計 | 5,297,800円 | |
| 2年次以降学費(年間) ※ | 4,200,000円 | |
| 6年間学費総額 | 25,800,000円 | |
※2年次学費を掲載しているため3年次以降の学費は記載と異なる場合があります
東邦大学医学部の奨学金
東邦大学青藍会(父母会)貸与奨学金貸与
| 金額 | - |
|---|---|
| 人数 | - |
| 目的 | - |
| 条件 | 在学生の父母(主として学費負担者)が経済的に困窮し、学納金の負担が困難と認められる場合に、学業維持を援助するために貸与することを原則としています。 |
| 免除 | - |
| 備考 | - |
東邦大学医学部の口コミ
合格するための口コミ(勉強法など)
- あなたが面接で聞かれた質問は何ですか。また質問にどのように回答しましたか。最低3つ教えてください。
- 【集団討論】
質問: 写真をみて
・この写真にタイトルをつけてください。
・この写真の作者は何を伝えようとしていると思いますか?
【MMI】
質問:...
- 受験生時代の英語の対策を具体的に教えてください。
- 文法が苦手だったため、文法の参考書を週に500問解くことを目標にし、答えを覚えるくらいまで繰り返しました。実際浪人していた1年間で7、8周したと思います...
キャンパスライフの口コミ(授業・サークルなど)
- 口コミ評価
 5.0点
5.0点
- 就職・進学
- -
- 授業・実習
- 5.0
- 部活・サークル
- 4.0
- 研究
- 5.0
- 国家試験・資格
- 3.0
- 恋愛・友人
- 4.0
- 施設・設備・立地
- 5.0
- 大学の授業や実習などカリキュラムで特徴的なところを教えてください。
- より良き臨床医の育成を教育目標として掲げており、全人的医療人教育という特徴的な科目があります。問題発見能力や課題解決能力、倫理的問題への対応力、コ...
- 口コミ評価
 5.0点
5.0点
- 就職・進学
- -
- 授業・実習
- 5.0
- 部活・サークル
- 5.0
- 研究
- 5.0
- 国家試験・資格
- 5.0
- 恋愛・友人
- 5.0
- 施設・設備・立地
- 4.0
- 大学の授業や実習などカリキュラムで特徴的なところを教えてください。
- CBT試験を3年生の1月に行うためか、全体的に基礎医学の講義を行う時期は早いと思います。そのため、一般科目的なものは1年生の一学期と二学期のみで、1年生の...
東邦大学医学部へのアクセス
| 所在地 | 東京都大田区大森西5-21-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行本線 梅屋敷駅 |
大学解説
[PR]東邦大学医学部におすすめの医学部専門予備校・塾・家庭教師
- 大学基本情報および受験・入試情報について
- 独自調査により収集した情報を掲載しております。正式な内容は各大学のHPや、大学発行の募集要項(願書)等で必ずご確認ください。
- 大学の画像について
- 東邦大学医学部の画像は654321さんから提供していただきました。


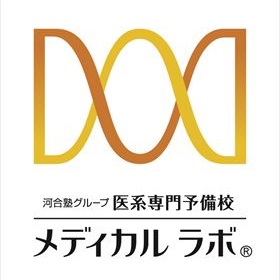







![全国進学個別進学塾 TOMEIKAI[トーメイカイ]](/yobikou/img/brand/316/logo.jpg?123456783234478689)






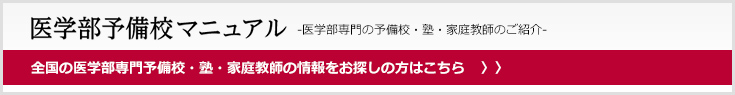











【歴史】 19ある旧制医専のひとつ。帝国女子医学専門学校を前身とし、東邦医科大学を経て、1950年東邦大学医学部となる。入試では付属校推薦枠を設けている。
【特徴】 1年次には基礎医学科目の授業があり、人体の構造や機能について器官・機能別に学び、正常な状態と疾病を患った異常な状態の違いを理解していく。3年次からは臨床医学の授業が始まり、テュートリアルと講義のハイブリット型授業で、器官・機能別に病因・病態・診断・治療について学ぶ。5年次からは、附属病院各科で38週間の基本的な臨床実習を体験する。