- 医学部受験マニュアルTOP
- 京都府の医学部一覧
- 京都大学医学部

| 口コミ |
|
|---|---|
| 偏差値 | 76.2(偏差値 2位/82校) ※医学部医学科がある全82大学での順位 |
|
学生数 ※医学部医学科の数値 |
666人【男性:81.2%・女性:18.8%】 (女子比率 41位/41校) |
| 6年間で 必要な学費 |
3,496,800円
|
| 医師国家試験 合格率 |
89%(合格率 75位/82校) |
京都大学医学部の偏差値
[PR]京都大学医学部におすすめの医学部専門予備校・塾・家庭教師
京都大学医学部の学費
| 6年間学費総額 |
3,496,800円
※国公立大は学費が一律のため
ランキングなし |
||
|---|---|---|---|
| 1年次学費総額 | 817,800円 | 2年次以降学費(年間) | 535,800円 |
| 1年次学費 | 入学金 | 282,000円 |
|---|---|---|
| 授業料 | 535,800円 | |
| 教育充実費 | -円 | |
| 委託徴収金 | -円 | |
| その他 | -円 | |
| 合計 | 817,800円 | |
| 2年次以降学費(年間) ※ | 535,800円 | |
| 6年間学費総額 | 3,496,800円 | |
※2年次学費を掲載しているため3年次以降の学費は記載と異なる場合があります
京都大学医学部の奨学金
授業料の免除
| 金額 | - |
|---|---|
| 人数 | - |
| 目的 | 授業料の納付が困難な学生(正規生のみ)に対して、次のいずれかに該当する場合は、選考のうえ、授業料の全額または半額の免除を受けることができます。ただし、出願時または出願期開始前6ヶ月以内に懲戒処分を受けた者または処分中の者は出願資格がありません。また、出願後に懲戒処分を受けた場合は、当該出願資格を無効とします。 |
| 条件 | 1.経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合 2.授業料の納付期限前6ヶ月以内(入学した日の属する期分の授業料免除の場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、または出願者もしくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合 3.2. に準ずる場合であって総長が相当と認める事由がある場合 |
| 免除 | - |
| 備考 | - |
京都大学医学部の口コミ
合格するための口コミ(勉強法など)
- あなたが面接で聞かれた質問は何ですか。また質問にどのように回答しましたか。最低3つ教えてください。
- ・入試の出来
・得意科目
・高校時代に頑張ったこと→部活、科学オリンピック
・京大志望理由→京都大学医学部に通っている同じ高校の先輩から「...
- 受験生時代の英語の対策を具体的に教えてください。
- 共通テスト 直前期に予想問題を使って時間を測って演習を行ったが、他にはしていない。
二次試験 高等進学塾の教材に、英文解釈は透視図、英作は竹岡先生...
キャンパスライフの口コミ(授業・サークルなど)
- 口コミ評価
 5.0点
5.0点
- 就職・進学
- -
- 授業・実習
- 5.0
- 部活・サークル
- 5.0
- 研究
- 5.0
- 国家試験・資格
- 4.0
- 恋愛・友人
- 3.0
- 施設・設備・立地
- 4.0
- 大学の授業や実習などカリキュラムで特徴的なところを教えてください。
- 全学共通科目は多様な科目から選択でき、少人数制のILASセミナーも多く設置されている。総合大学であるため、医学以外の分野でも専門家の講義を受けることが...
- 口コミ評価
 5.0点
5.0点
- 就職・進学
- -
- 授業・実習
- 5.0
- 部活・サークル
- 5.0
- 研究
- 3.0
- 国家試験・資格
- 5.0
- 恋愛・友人
- 4.0
- 施設・設備・立地
- 5.0
- 大学の授業や実習などカリキュラムで特徴的なところを教えてください。
- 京都大学は基本的に他の大学の医学部に比べて楽だと言われており、実際そのように感じる。そのおかげで勉強以外の色々な活動ができ、楽しい学生生活が送れる...
京都大学医学部へのアクセス
| 所在地 | 京都府京都市左京区吉田本町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 神宮丸太町駅 |
大学解説
[PR]京都大学医学部におすすめの医学部専門予備校・塾・家庭教師
京都大学医学部と偏差値の近い 国公立大学
京都大学医学部を見ている人はこんな大学も見ています
- 大学基本情報および受験・入試情報について
- 独自調査により収集した情報を掲載しております。正式な内容は各大学のHPや、大学発行の募集要項(願書)等で必ずご確認ください。
- 大学の画像について
- 京都大学医学部の画像はMojaから提供していただきました。




![全国進学個別進学塾 TOMEIKAI[トーメイカイ]](/yobikou/img/brand/316/logo.jpg?123456783234478689)


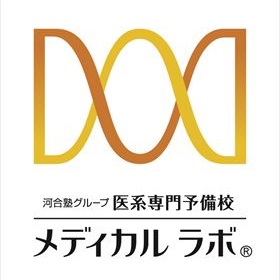







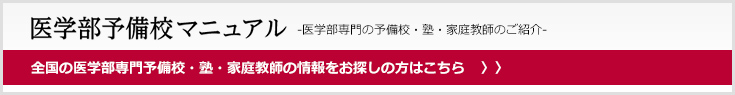










【歴史】 歴史と伝統を誇る「旧帝国大学」7校のひとつ。京都帝国大学医学部を経て、1951年に新制京都大学医学部が発足。「再生医科学研究所」はiPS細胞の世界的権威であり、医師一人当たりが発表した臨床論文数では堂々の全国一位である。
【特徴】 入学後直ちに、すべての学生が基礎医学生物学の授業を通じて少人数輪読会に参加し、早期より生命科学の基本概念を学びはじめる。また、早期から学生個々の知的好奇心や研究を育む目的で、ラボローテーションの制度を導入し、関心の高い学生に対しては早期から研究室での生命科学研究を体験する機会が与えられる。5年次以降の臨床医学実習においては、単なる見学を排除し、患者受け持ちとなり、実際の医療サービスの中でチーム医療に貢献しながら、自律的に臨床能力を身につけることが求められる。